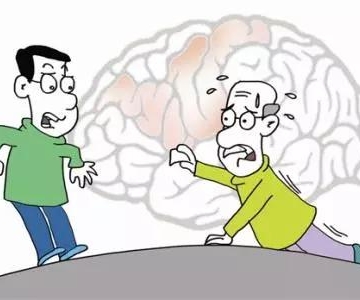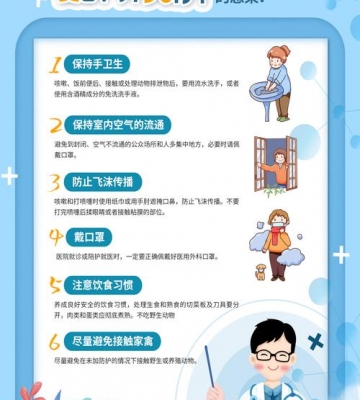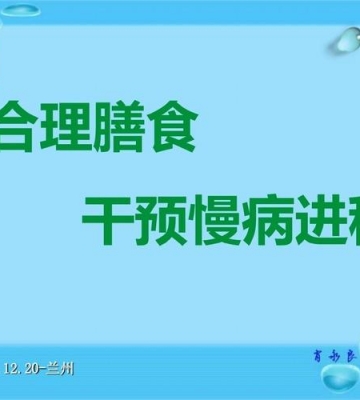史
日本血草(けっそう)は、日本の伝統的な植物であり、古くから栽培されてきました。血草は難しい栽培を要する植物であり、多くの地方の民間伝承によって長年にわたって継承されてきました。
日本初の栽培血草は古代から中世にかけて使用されていましたが、実際の大規模な栽培が始まったのは17世紀後半から18世紀前半の頃です。当時、血草栽培の研究者と呼ばれる専門家が存在し、彼らは血草の産地を広げることを目的としていました。19世紀以降も多くの地方で血草が栽培され、文化的価値も高くなりました。20世紀以降も昭和時代以来の政府の支援を受けながら多くの地方で血草が栽培されてきました。
近年では文化的価値だけでなく医学的効力も語られるようになり、国内外から注目を集める存在となっています。今後も日本の伝統的な植物として野生性の高い血草の産地を広げることに努める必要性があります。